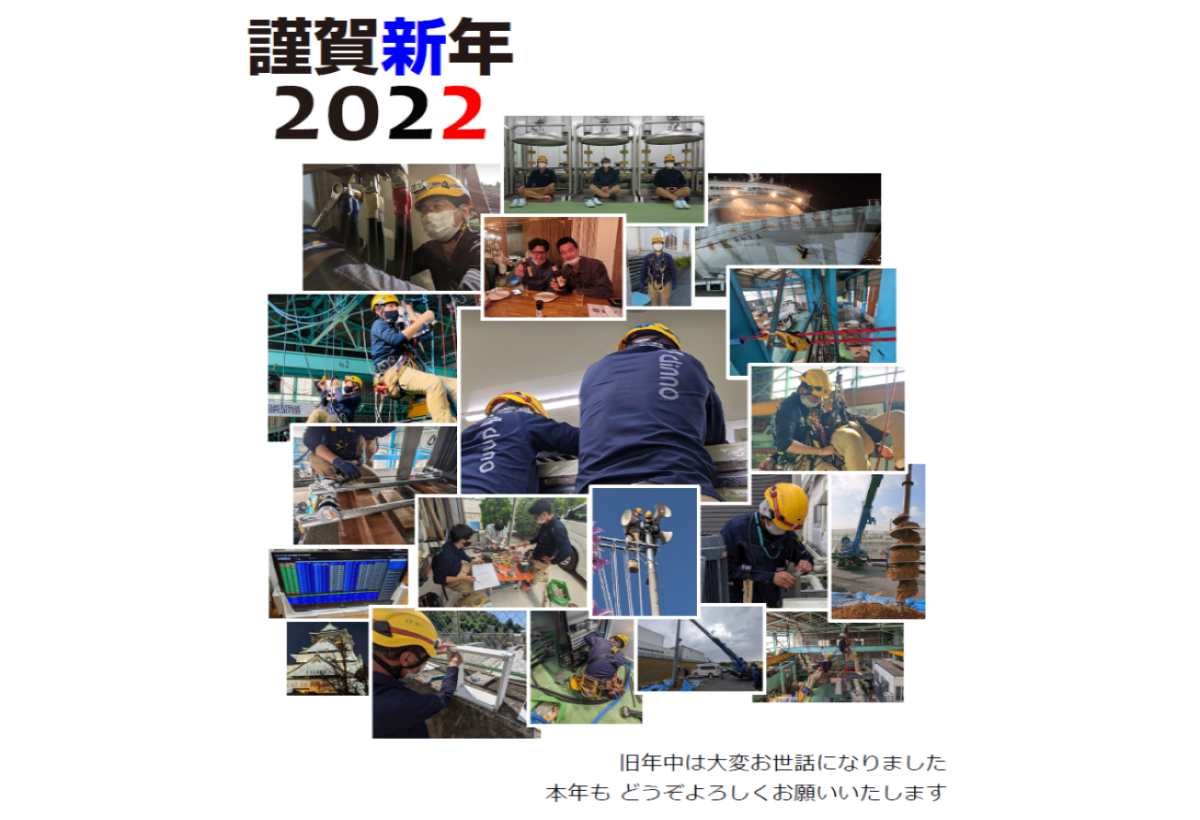カメラ録画システム(防犯カメラ・監視カメラ)の選定とメンテナンスのポイント
カメラシステムに携わる中で、お客様からよく相談される内容としてシステムの選定とメンテナンスに関することが多いように思います。そんな中でお答えしてきた事をこちらにまとめてご案内させていただきます。
目次
1.カメラシステムの選定方法
-1.1 耐久性から選ぶ(カメラ本体)
-1.2 配線方法から選ぶ
-1.3 録画方法で選ぶ(レコーダー)
2.カメラシステムのメンテナンス
-2.1 オンプレ録画レコーダーのメンテナンスについて
-2.2 バックアップ電源
1.カメラシステムの選定方法
防犯、監視カメラ、品質保証カメラなどカメラの用途はさまざまです。また最近ではホームセンター等でも格安の機材が簡単に手に入ります。そんな中からどんな商品を選択すればよいか、普段弊社がお客様にお話ししている事をご紹介させていただきます。何かの参考になれば幸いです。
1.1 耐久性から選ぶ(カメラ本体)
利用されたい場所はどのような場所でしょうか?工場、店舗、住宅などシーンによってさまざまだと思います。
耐久性を必要とされるのは工場や店舗などの業務利用の場合。特に高所への取付となると簡単に交換できませんのでなおさらですが、頻繁に故障されてはメンテナンスにお金がかかって仕方ありません。また常時モニタリングしているような環境では映らなくなった時点で業務に支障が出ます。このような場合は耐久性で実績のあるAxisやCanon,Panasonicといった業界では誰でも知っているようなカメラメーカーを選択される方が良いかと思います。弊社案件ではほぼAxis製のカメラを使用してますが、5年保証が標準で付帯されておりメーカーの商品に対する自信が伺えますし、今まで相当な数のカメラを設置していますが実際そう簡単には壊れていません。
それでは一般住宅でご利用される場合はいかがでしょうか?一般住宅で使用するカメラの場合耐久性が低くても良いかといえば実際はそうではなく、おそらく予算が合うなら耐久性のあるものを設置されたいと思います。カメラメーカーもかなりの種類があり、聞いたことが無いようなメーカーの物も普通に販売されていますのできっと選択に困ることでしょう。インターネットで検索していると「カメラ4台とレコーダーセットで10万円」といったようなかなり廉価な商品が販売されています。これらの製品、実は映り自体はそこそこ良いものもあります。ただ、やはり映りが良くても耐久性に関しては別の話です。実際ネットで購入された安いカメラをお客様に依頼されて設置したことが何度かございますが、やはり2~3年程でカメラそのものの映りが悪くなったりレコーダーが故障したりといった不具合が出るケースがありました。耐久性に関しては弊社の経験としてもある程度価格と相関関係があるように思いますので、安いものは耐久性もそれなりだと思ってよいかと思います。
耐久性の観点で見ると、壊れても困らないような利用用途、もしくはご自身で設置される場合でいつでも修理できるような取付場所である、そしてとにかく安いほうがいいという場合は廉価品も選択肢とし、業務利用や一般家庭でのご利用でも頻繁に壊れるのは困るという場合、そして予算が合う場合は耐久性と保証が期待できる一流メーカーの物を選択されるのが良いと思います。

1.2 配線方法から選ぶ
カメラを単独で設置し、カメラ本体に挿入したSDカードに録画する場合は電源さえあれば単独で完結しますのであまり関係の無い話になりますが、複数台のカメラ構成で、別途レコーダーに接続してそちらで録画する場合、この配線方法の違いが施工費用に大きく影響します。カメラの台数が増えれば増えるほどその影響が大きいのですが、この配線方法にはどんな種類があるかご存じでしょうか?
アナログカメラとネットワーク(IP)カメラ
カメラ4台程度でレコーダーに直接モニターを接続するような小規模な環境であればアナログカメラでも十分対応可能です。しかし、カメラ台数が50台や100台といった規模になると、レコーダーに向けて同数の配線が必要となり、配線が煩雑化するため、レコーダーの設置場所には配線集約の工夫が求められます。もちろんシステム構築は可能ですが、配線の多さは管理上の課題となります。
一方、ネットワークカメラはスイッチングハブで集約できるため、大規模なシステムでもレコーダーへの配線は集約され、運用中のカメラ増設も最寄りのハブまでの配線で済むため容易です。
ただし、アナログ・ネットワークカメラ共通の注意点として、レコーダーの機種には接続可能なカメラ台数の上限があるため、将来的な増設の可能性を考慮した上で機種選定を行うことが重要です。特にアナログカメラの場合、後からの増設には新たな配線工事が必須となるため、増設の予定がある場合は、事前に配線だけを敷設しておくなどの対策が望ましいです。
また、実際にはネットワークカメラの一部で同軸ケーブルが使用されたり、アナログカメラでもレコーダーがネットワークに対応しているケースも存在します。既存のシステムへの増設を検討されており、機械操作に不慣れな場合は、配線だけで判断せずに専門家への相談をお勧めします。
配線方式による選択の目安としては、小規模(8台程度まで)な環境であればアナログカメラとネットワークカメラのどちらも選択肢となり得ますが、中規模から大規模な環境においては、ネットワークカメラを選択するのが一般的と言えるでしょう。
1.3 録画方法で選ぶ(レコーダー)
録画方法は大きく分けて以下の4種類
- 1.録画しない(モニタリングのみで使用)
- 2.カメラ本体に挿入したSDカードで録画
- 3.レコーダーで録画(オンプレミス録画タイプ)
- 4.インターネット越しにクラウドで録画(クラウド録画タイプ)
1. 録画しない(モニタリングのみ)
録画機能は不要で、リアルタイムの映像監視のみを行う場合です。HDMI出力端子付きのカメラであれば、モニターに直接接続するだけで最小限のシステムを構築できます。
2. カメラ本体のSDカードで録画
主に駐車場や自治体の防犯カメラなどで採用される方式です。通常は映像を確認せず、有事の際にカメラからSDカードを取り出してPCでデータを確認します。電源があれば単独で機能するため安価に導入できますが、SDカードには書き換え寿命があり、定期的な録画状況の確認を怠ると、必要な時に映像が記録されていない可能性があります。
3. レコーダーで録画(オンプレミス)
カメラを設置する建物や敷地内にレコーダー(録画サーバー)を設置する一般的な方式です。カメラ台数に合わせてレコーダーのチャンネル数を選定します(通常4の倍数)。アナログカメラの場合は1台のレコーダーで8台程度、ネットワークカメラであれば64台程度までが目安となり、それ以上の場合は複数台のレコーダーでシステムを構築します。
SDカード録画と同様に時刻同期の管理が重要で、インターネット接続がない環境では、GPSやラジオ電波を受信するNTPサーバーの別途設置が必要です。また、レコーダー内蔵のハードディスクにも寿命があり、一般的に20,000~25,000時間でエラーが発生し始めるため、定期的なメンテナンスが必要です。業務利用の場合は、2ヶ月に1回程度の保守メンテナンスが推奨されます。多くのシステムではRAID構成によりデータ損失のリスクを低減していますが、複数台のハードディスクが同時に故障した場合はデータ復旧が困難になることがあります。
4. インターネット越しにクラウドで録画(クラウド録画タイプ)
レコーダーが不要で、インターネット回線と月々のランニングコストが発生します。初期投資を抑えられ、カメラ台数の増減にも柔軟に対応可能です。全国に拠点がある企業でも、容易に同一プラットフォームで録画システムを構築・管理できます。レコーダーのメンテナンスが不要であり、「99.999999999%(イレブンナイン)」という非常に高いデータ耐久性が特長です。ただし、安定したクラウド録画のためには、ネットワーク環境の整備が不可欠です。
2.カメラシステムのメンテナンス
前項で述べたように、カメラシステムの安定稼働には定期的なメンテナンスが重要です。ここでは、特にオンプレミス録画システムで使用されるレコーダーのメンテナンスとバックアップ電源について詳しく解説します。
2.1 オンプレミス録画レコーダーのメンテナンス
カメラ映像を記録する上で必須となるレコーダーですが、クラウド録画の高い耐久性(イレブンナイン)に対し、オンプレミス環境ではユーザー自身によるメンテナンスが重要となります。監視カメラシステムはカメラの存在が強調されがちですが、その背後には録画を行うオンプレミスサーバーが存在することが一般的です。これらのサーバーには、PCと同様のハードディスク(高価なシステムではSSD)が使用されており、24時間365日稼働し続けると、約2~3年でエラーが発生し始め、最終的には故障に至り、必要な時に録画データが取り出せなくなる可能性があります。
このような事態を防ぐためには、以下のメンテナンスが有効です。
1. 定期的な給排気部分の清掃: レコーダーは動作中に熱を発生させるため、ファンによる給排気機構を備えています。特に事務所などのサーバー専用室ではない場所に設置されている場合、給気口に埃が詰まりやすく、本体温度の異常な上昇を招き、内部基盤やハードディスクの故障、レコーダー本体の寿命低下につながります。清掃の際は、不用意なボタン操作や濡れた布巾の使用は避け、慎重に行ってください。
2. 定期的なシステム状態の確認: ある程度のPCやサーバーの知識が必要となるため、自信がない場合は専門部署や専門業者に依頼してください。企業で使用されるレコーダーには、通常、エラーを検知するシステムログ(エラーログ)機能が搭載されています。このログを定期的に確認することで、ハードディスクのエラーだけでなく、ネットワークやカメラの異常、本体の温度異常、録画システムの状態など、様々な問題を早期に発見し、部品交換などの対策を講じることで、レコーダーの安定稼働とデータ消失のリスクを低減できます。比較的新しいレコーダーには、エラー発生時に外部へメール通知したり、警告灯(パトライト)を点灯させる機能が搭載されている場合もあり、これらを活用することでメンテナンスの手間を軽減できます。
2.2 バックアップ電源(UPS)
近年、ゲリラ豪雨などによる落雷や急な停電が増加傾向にあり、カメラシステム、特にレコーダーは予期せぬ電源断に備える必要があります。レコーダーはPCと同様に、通電中に突然電源が遮断されると、回転中のハードディスクに不具合が生じ、故障の原因となることがあります。このようなリスクを軽減するために有効なのが無停電電源装置(UPS)です。
UPSは内蔵バッテリーにより、停電時に接続された機器への電力供給を一時的に継続する装置ですが、バッテリー容量には限りがあるため、長時間の停電に対応できるわけではありません。重要なのは、停電発生時にUPSの電力供給が途絶える前に、レコーダーを安全にシャットダウンさせることです。
多くのレコーダーには、UPSと連携して動作する機能が備わっており、例えば「商用電源が3分以上途絶えた場合にレコーダーへ信号を送り、信号を受信したレコーダーが自動的に正常シャットダウンを行う」といった設定が可能です。また、商用電源が復旧した際には、自動的に元の状態に復帰させる設定も行えます。これらの機能を利用するためには、UPSとレコーダーをUSBケーブルや専用ケーブルで接続し、事前に設定を行う必要があります。
UPSの主な役割は、商用電源断時にレコーダーへ信号を送り、安全なシャットダウンを促すこと、そして電源復旧時に元の状態へ復帰させることです。設定によっては、停電後にシャットダウンしたままにしたり、復旧後も起動させないといったカスタマイズも可能です。
さらに、UPSは落雷による過電流からも接続機器を保護する役割を果たします。直接コンセントに接続するよりも、雷による故障のリスクを大幅に低減することができます。
まだまだお伝えしたいことはありますが。。。
随分と長くなってしまいましたので今回はこの辺で。カメラの導入、またはリプレイスなどのご相談がございましたらお気軽にdinnoにご連絡ください。カメラだけとかレコーダーだけといった更新も可能ですし、クラウド録画システムも選択いただけます。オンプレ録画、クラウド録画どちらにもそれぞれ長所短所がございますしお客様によってその長所短所となる部分が異なりますので一つのシステムだけを押し付けるようなご提案は致しませんので安心してご相談ください。